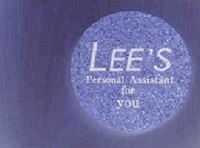Personal Assistant for YOU LEE'S リー・ヤマネ・清実
LEE'Sは、リー・ヤマネ・清実の個人事務所です。1991年に経営トップの経営企画業務を外部から適時アシストする業を“パーソナル・アシスタント”と名づけて出発、独自なスタイルとスタンスを探究しながら現在に至っています。1995年事務所開設、1996年中小企業診断士登録
・経営略系コンサルティング−経営と人生の道すじを計る
・自業コンサルティング−自分ならではの仕事と生き方を自身で見出す、見定める

事務所を開設した1995年以来、仕事や日常の中で感じ考えたことを記録し続けています。
『ひとりひとりの人間は、もし自分をこまかく観察する能力を持っているならば、自分自身にとってひじょうによい教育材料になる』(『モンテーニュ』荒木昭太郎 2000年)
「読書をする」ことは無形の恵みをもたらしてくれ、自業探究の下支えになっています。
◆「考える時間をつくる」

『精神医学的面接』
2025/12/26−
『易経』(丸山松幸訳)
2025/7/19−2025/12/25
『最終講義』中井久夫
2025/4/24−2025/7/18
『数学する人生 岡潔』
2024/8/9−2025/4/23
『アリアドネからの糸』
2024/7/9−2024/8/8
『中井久夫集3』
2024/2/19−2024/6/19
『モンテーニュ』
2023/10/12−2024/2/13
「老子」訳注再読
2023/8/21−2023/10/3
『孫子 金谷治訳注』
2023/1/10−2023/4/18
『哲樂の中庭』(2001年7月)

【インタビュー記事】
「CREO」2021年7月-10月号に「女性チャレンジ応援拠点のインタビュー記事
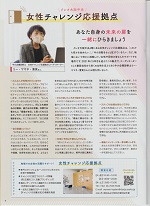
【寄稿】
2020年6月
「未来を創る10の視点 withコロナどう生きる?」特集

●2016年7月
〒541-0046
大阪市中央区平野町1-7-1
堺筋高橋ビル5FB507
info@leeslee.com

【アクセス】
地下鉄堺筋線北浜歩2分
御堂筋線淀屋橋歩8分
■外出の予定2026年
(在所は8:00-16:00)
日 |
曜 |
am |
pm |
|---|---|---|---|
1/5 |
月 |
(在) |
(在) |
1/6 |
火 |
(在) |
(在) |
1/7 |
水 |
(在) |
夕陽ケ丘 |
1/8 |
木 |
(在) |
(在) |
1/9 |
金 |
(在) |
(在) |
◆ご案内-先を読む助けに
・俯瞰(ふかん)塾リリース
・俯瞰塾パーソナル(予約)
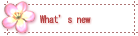
◆「日常を観察する」
・essais 〈書く〉2026年1月
・essais 〈書く〉2025年12月
・essais 〈書く〉2025年11月
・essais 〈書く〉2025年10月
・essais 〈書く〉2025年9月
・essais 〈書く〉2025年8月
・essais 〈書く〉2025年7月
・essais 〈書く〉2025年6月
・essais 〈書く〉2025年5月
・essais 〈書く〉2025年4月
バックナンバー
◆ 「自問自答を続ける」
リーズレター『哲樂の中庭』
・2025年11月7日立冬

バックナンバー
◆「令和」記念リーズレター
2019年4月5日清明
(5月から「令和」を機に)

【記事関連】 2021年6月11日にポスターのプレゼント、机の正面で見守ってくれているよう

◆「考える時間をつくる」
(観る、歩く、考える
2025年
| 12/25 | 『精神医学的面接』 |
| 12/15 | 小さな作品展 |
| 7/19 | 『易経』 |
| 4/24 | 『最終講義』 |
2/10 |
『日月ギャラリー』 |
LEE'S リーズ
 |
- 学びをかさねて -
この3月で事務所開設30周年をむかえました。1995年は社会の大きな転換点でした。その後の変化を同時代で生きながら、LYK流パーソナル・アシスタントの実践を模索し今にいたっています。
たかだか30年、されど30年。2月3日立春リーズレターに書いたように、模索のなかで大切で貴重な学びを得られ、〈自分に試練を与える〉直感と実行は功を奏したと思えます。
学びはうそをつかない。学びに応じて人の役にも立てる、昨年来そう実感じています。これからも、無理はせず、でも学びはかさねて、あなたの歩みをよりよくアシストできるよう、31年目を始めます。
2025年4月1日 リー・ヤマネ・清実

◆日常を観察する essais〈話す&書く〉
−『精神医学的面接』音読のためし−
2026年1月9日 序 本書は、概要手引書ではなく…
2026年1月9日(金) 曇・晴
早朝は雲っていた。徐々に晴れてきて、夜にかけて晴天の予報。気温は低いけど風はよわい。三連休、月曜は荒れそう。
―おさらい独習 「六十四卦」― 18.蠱
「こ」、皿に盛った食物に虫がわいていること。解説に「泰平が続けば内部に腐敗と混乱が進行する。まことに多事多難」。
しかし、「窮すれば通ず、矛盾が深ければ深いほど逆に根本的解決が可能となる。革新、新生のとき」。
原文には改革に臨む際の貴重なポイントが示されている。
「今や改革のとき、新時代の創造にあたっては、ここに至った経過と今後の展開を、慎重に考慮してかからねばならぬ」。
この卦はイメージしやすい。官僚主義的になった大企業、ワンマン経営者の企業風土、など等。
親の創業した会社が行き詰まり、子が意を決して社長に就任し、再起をはかるケースもよくある。
ところでこの「蠱」を『イクザガミ』の新聞広告で見た。ネトフリの配信で世界的なヒットになっているドラマ。
広告によると、「蠱毒」というデスゲームを描く物語りとか。原作者は『易経』からヒントを得た?
(事象) 世代交代、事業継承。過去を検証し、未来の展望を明確に描き、やるべきことを率先して実行すれば危難を克服できる
(心得) 「社員たちを守る。改革にあたって、社員たちの不安を払拭し、会社に希望がもてるような方策を講じる」
(構え、パノラマ)
一、先代の「負の遺産」を処理する。創業精神は尊重して、改革を実践すれば、リスクは伴うが、乗り切る
二、先代の社外活動にメスをいれる。先代の社会的な体裁が保てるよう施す
三、処理を徹底する。内心やりすぎの気持ちがあっても、対外的に示しがつく
四、先代の苦境をただ傍観する。危機がしのびよる
五、改革を果たす。先代の創業精神を引継ぎつつ、会社の企業文化を刷新する
六、自立して新しい代を創る。先代の何もかも引き継がず、一から自分の代をつくる
以上、「蠱」のおさらい。最後の六番目の原文は、「王侯につかず、野にいて一身を高潔に保つ。その志は模範とするに足る」。
これをどう解釈すればいいか、考えが浅くて、あまりしっくりこないが仕方ない。それでもそこそこ頭の体操になっている、このおさらい。

−Personal Assistant for You LEE'S−
*2024年3月27日(